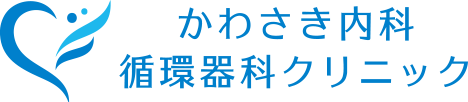- HOME>
- 不整脈(心電図異常)
こんなお悩みはありませんか?
- 最近、動悸や胸の違和感を感じることがある
- めまいや息切れが突然起こることがある
- 脈が不規則になったり、速くなったりして不安を感じる
- 健康診断で「不整脈」と診断されたが、どう対応したらよいか分からない
これらの症状は、不整脈によって引き起こされている可能性があります。不整脈は、軽度の場合でも日常生活に影響を与えたり、放置すると深刻な合併症を引き起こしたりすることがあるため、適切な診断と治療が大切になります。
不整脈とは?
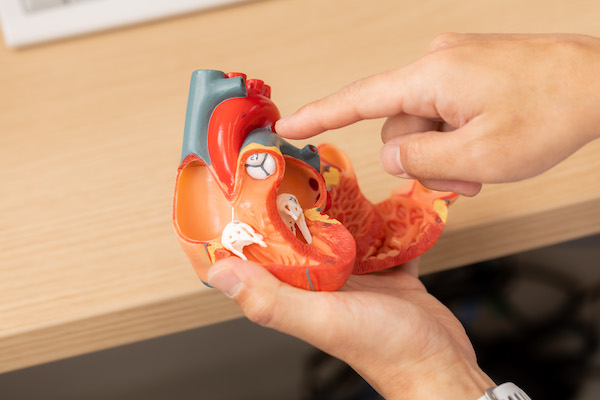
不整脈とは、心臓の鼓動が通常のリズムから外れ、遅くなったり(徐脈)、速くなったり(頻脈)、あるいは不規則になる状態を指します。健康な心臓では、リズムが規則的に保たれていますが、不整脈が発生すると血液の循環に影響を及ぼし、さまざまな症状を引き起こします。
不整脈の原因
不整脈には、生理的なものと病的のものがあります。
生理的な不整脈
運動、精神的ストレス、発熱などによって一時的に起こるものをいいます。
病的な不整脈
心臓病(心筋梗塞、弁膜症、心筋症など)や高血圧、加齢などが原因となるものです。
その他の不整脈
不整脈は特定の薬剤や、喫煙、過度な飲酒、睡眠不足などの生活習慣によって誘発されることもあります。
不整脈の種類と特徴
不整脈は、心臓の拍動が通常のリズムから外れる状態を指し、主に次のような種類に分類されます。
徐脈(じょみゃく)
特徴
心拍数が1分間に50以下に減少する状態です。
心臓の「発電所」である洞結節や、心房から心室に電気を伝える「電線」の異常が原因となる場合があります。
症状
息切れやめまい、疲労感などがあり、重症の場合は、意識を失うことや失神(アダム・ストークス発作)が起こることがあります。
原因
洞不全症候群、房室ブロック、加齢に伴う心臓の機能低下、薬剤(降圧薬や強心薬)など。
治療法
症状が強い場合や重症例では、ペースメーカーの植え込みが必要になることがあります。
頻脈(ひんみゃく)
特徴
心拍数が1分間に100以上になる状態です。
運動やストレスなどによる一時的なものと、病的な頻脈に分けられます。
症状
動悸や胸の不快感、息切れ、めまいなどがあり、胸痛や失神が起こることもあります。
原因
心房性頻脈、心室性頻脈、発作性上室性頻拍(WPW症候群など)。心筋梗塞や心筋症などの基礎疾患に伴う場合もあります。
治療法
抗不整脈薬やカテーテルアブレーションなどの根本治療がおこなわれます。心室頻拍の重症例では、植え込み型除細動器(ICD)の使用が検討されることがあります。
期外収縮(きがいしゅうしゅく)
特徴
通常のリズムから外れたタイミングで心臓が収縮する状態です。
心房性期外収縮(心房由来)と心室性期外収縮(心室由来)に分類されます。
症状
のどや胸の違和感、動悸。脈が飛ぶなどの症状があり、症状が強い場合にはめまいが生じることもあります。
原因
運動不足、ストレス、睡眠不足、疲労などが主な原因です。しかし一部は心筋梗塞や心筋症などの病気に関連することがあるため注意が必要です。
治療法
症状が軽度であれば経過観察で様子を見ます。症状が強い場合には抗不整脈薬や安定剤を使用します。
洞不全症候群
特徴
洞結節の機能が低下し、心拍数が著しく遅くなる状態です。徐脈と頻脈が交互に現れることがあります(徐脈頻脈症候群)。
症状
めまいやふらつき、失神などがあり、症状が進行すると心不全を引き起こすこともあります。
原因
加齢による洞結節の老化、薬剤の影響などがあります。
治療法
症状が重い場合はペースメーカー治療がおこなわれます。
房室ブロック(ぼうしつブロック)
特徴
心房から心室に電気信号が伝わりにくくなる状態です。
重症度に応じて、1度、2度、3度(完全房室ブロック)に分類されます。
| 分類 | 特徴 | 症状・影響 |
|---|---|---|
| 1度 | 心房から心室への電気信号が伝わる速度が遅いが、全ての信号が伝わる。 | 軽度では無症状。心電図で偶然発見される場合が多い。 |
| 2度 | 一部の電気信号が心室に伝わらない。モビッツ1型とモビッツ2型の2種類に分類 | 疲労感やめまいが見られる場合がある。 |
| モビッツ1型(ウェンケバッハ型) | 信号伝達が徐々に遅くなり、ついに1つの信号が途切れる。比較的軽症で経過観察がおこなわれることが多い。 | |
| モビッツ2型 | 突然、信号が伝わらなくなる。より重篤で治療(ペースメーカーの植え込みなど)が必要な場合がある。 | |
| 3度 | 完全房室ブロック。全ての電気信号が心房から心室に伝わらなくなる。 | 重度の症状(めまい、失神、心不全)が見られ、ペースメーカーの植え込みが必要。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
原因
心筋梗塞や心筋症などの基礎疾患、または迷走神経の影響により起こります。
心房細動(しんぼうさいどう)
特徴
心房が細かく震える状態で、心房の収縮が不規則になります。心房細動が続くと血流が滞り、血栓が形成されるリスクがあります。
症状
動悸、息切れ、めまい、胸部不快感、また、無症状の場合もあります。
原因
高血圧、心筋症、弁膜症、加齢による心臓機能の低下などにより起こります。
治療法
- 脳梗塞予防のための抗凝固療法
- 心房細動を根本的に治すカテーテルアブレーション
WPW症候群(ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群)
特徴
生まれつき心房と心室の間に余分な伝導路(副伝導路)があることで発生する不整脈です。
頻脈が突然始まり、突然止まる発作性上室性頻拍が特徴的です。
症状
強い動悸、息切れ、めまいなどがあり、症状が続く場合は日常生活に支障が出るケースもあります。
治療法
抗不整脈薬やカテーテルアブレーションが有効です。
その他の不整脈
心房粗動
心房内で規則的に電気信号が旋回する不整脈。心房細動に似ていますが、治療法は異なります。
右脚ブロック・左脚ブロック
心臓の伝導路の一部が障害される状態。通常は無症状ですが、重症例では心機能低下を引き起こすことがあります。
ブルガダ症候群
特定の心電図パターンを伴い、突然死のリスクがある病気です。
かわさき内科循環器科クリニックの不整脈の検査と治療について

不整脈は心臓のリズムに異常が生じる病気で、場合によっては命に関わることもあります。そのため、正確な診断と適切な治療を受けることが非常に重要です。
当院では、不整脈の早期発見と適切な治療を最優先としています。長年大学病院の第一線で心臓疾患治療に尽力してきた専門医が在籍しており、その豊富な経験を活かして、必要な検査や治療を迅速かつ的確におこないます。
患者さまの何気ないお話にも耳を傾けることで、心臓の異常を見逃さず早期に発見することを心がけています。また、生活習慣の改善やストレス管理など、病気の予防に向けたアドバイスもおこない、患者さまお一人ひとりに寄り添った治療をご提供しています。
「不整脈は怖い病気かもしれない」と不安に感じる方も多いですが、適切な診断と治療でそのリスクを大幅に軽減できます。不整脈に関するお悩みや疑問がある場合は、ぜひ当院にご相談ください。
不整脈の検査と診断方法
当院では、長年にわたり心臓疾患の治療に携わってきた専門医が在籍しており、不整脈の早期発見と正確な診断に力を入れています。不整脈の特定には、以下のような検査がおこなわれます。
心電図検査
心臓の電気的活動を記録し、不整脈の種類や異常を確認します。
ホルター心電図
24時間心電図を記録することで、日常生活中に発生する不整脈を検出します。
運動負荷検査
運動中の心臓の動きを観察し、症状の原因を調べます。
心エコー検査
心臓の構造や機能を超音波で確認し、不整脈の原因となる異常を探ります。
カテーテル検査
より詳細な診断が必要な場合、カテーテルを用いて心臓内部の状態を精密に調べます。
不整脈の治療
不整脈の治療法は、症状の重さや原因疾患の有無に応じて異なります。当院では最新の医療技術を用いて、それぞれの患者さまに適した治療をおこなっています。手術が必要な場合には、すみやかに提携の医療機関と連携をとりご紹介させていただきます。当院には、循環器専門医による心臓リハビリテーションにも力を入れておりますので、退院後のサポートもしっかりとご対応させていただきます。
治療を受ける前に知っておくべきこと
- 症状の原因やリスクについて医師から十分な説明を受けるようにしましょう。
- 合併症や手術リスクをしっかりと確認しましょう。
- 定期的な検査を受け、経過観察を続けましょう。
不整脈の予防と生活習慣の改善
不整脈を予防し、健康な心臓を保つには、生活習慣がとても重要です。
バランスの良い食事
塩分を控えめにし、脂肪は植物性を中心に摂取しましょう。
適度な運動
20〜30分程度の有酸素運動を習慣にしましょう。
禁煙
喫煙は心疾患のリスクを大幅に高めるため、禁煙を心がけましょう。
ストレス管理
過度なストレスを避け、心身のリラックスを心がけましょう。